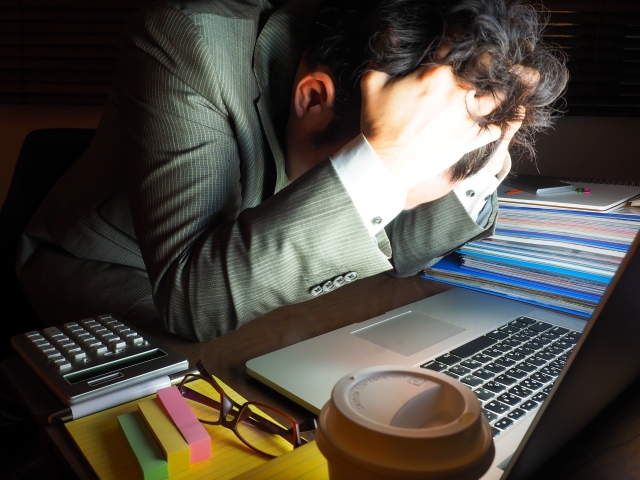
上島竜兵、渡辺裕之、神田沙也加と続けて報道されている著名人の自死のニュースに、多くの人が衝撃を受けた。順風満帆な人生で傍から見ると「なぜ」と思わずにはいられない。しかし、これは自殺問題の一端を示している。
統計によれば、日本では自殺により毎年多くの命が失われている現実がある。もしかすると身近に自殺しそうな者がいるかも知れない。自殺をくい止めるためにもそうした自殺予備軍の出すサインを見逃さないようにしなくてはならない。
日本における自殺問題の現状
自殺問題は、個人だけでなく社会全体で取り組むべき深刻な課題である。日本で自殺する人の背景には、経済的困窮、人間関係の悩み、健康問題など複合的な要因が絡み合っている。特に近年、コロナ禍以降の社会環境の変化が、メンタルヘルスに大きな影響を与えていることも指摘されている。
自殺問題への理解を深めることは、命を守るための第一歩となる。周囲の人々が適切な知識を持ち、早期に異変に気づくことができれば、救える命は確実に存在する。
希死念慮とは何か
自死の原因はさまざまなものがあるが、自殺者の97%は精神疾患があると言われる。しかし、精神疾患がある者が全て自殺をするわけではないので、自殺をしてしまう者の特徴として自殺をしやすい性格があると説かれている。
この自殺をしやすい性格とは何かというと希死念慮だ。概念的に、私はこの状況を「死神に魅入られた」状態と思っている。
希死念慮は、文字通り「死にたい」という思いが心の中に湧き上がってくる状態を指す。これは単なる一時的な気分の落ち込みとは異なり、持続的に死について考えてしまう精神状態である。
昔、知り合いにこの希死念慮がある人がいた。しきりに死にたいと言っていた。かと言って、うつ病などではなく、元気に仕事をしている。「世の中、楽しいこともいっぱいある」と伝えても「確かにそうだが」とは言うが、だからと言って希死念慮が消えるわけではない。希死念慮とは、頭の中に湧いて出て来る理屈が通らないもののようだ。
うつ病と自殺の関連性
うつ病で死亡するケースについて理解することは重要である。うつ病は自殺の大きな危険因子の一つであり、適切な治療を受けずに放置すると、死にたいという思いが強まり、最悪の場合うつ病で死亡する結果につながることがある。
うつ病の症状としては、持続的な憂うつ気分、興味や喜びの喪失、睡眠障害、食欲の変化、疲労感、集中力の低下などが挙げられる。これらの症状が2週間以上続く場合は、専門医への相談が必要である。
うつ病で死亡することを防ぐためには、早期発見と早期治療が不可欠だ。本人が死にたいと訴えている場合は特に注意が必要で、すぐに医療機関や相談窓口につなげることが重要である。
元気に見える人の自殺
また、「故人サイト」という本がある。お亡くなりになった方々が生前作成していたサイトを様々な視点から解説をしている。
当然、中には自死した人のサイトも紹介しているのだが、自殺する前は、皆、それなりに元気でいた雰囲気を漂わせている。
表面上だけ元気そうにしていたということも考えられるが、私は、皆、希死念慮はあったものの、それなりに元気だったのではないかと推測している。
つまり、自死は、うつ病が高じて希死念慮が生ずる場合と、希死念慮が単独で生ずる場合があると思っている。何れにしても希死念慮があって次に自殺願望があって自殺となることには間違いない。
こうして考えると、やはり希死念慮は「死神に魅入られた」ときに生じると概念的に思っても間違いではないようだ。
何を言いたいかということだが、死神が本当にいるということではない。外形上死にそうにない人が自殺してしまうという現実があるということだ。これは日本で自殺が起きる際の特徴的な側面でもあり、周囲が気づきにくい理由の一つとなっている。
私の体験から学んだこと
長く人間をやっていると色んなことがある。
そのひとつに、私の身近でも自死する者が出た。
職場の同僚であるが、その人は、遅れず、休まず、深夜まで働いていた。普通、自殺しそうなメンタルであれば、うつ病のような雰囲気があるだろうが、そのようなことは全くなかった。
そうであったからこそ、彼が自死を選んだときは驚いた。
一般的には、自殺しようとする人は、いつもと違う行動が見られるようになるというが、全くそのようなことはなかった。
恐らく、何らかのサインはあったのであろうが、会社でそこまで認知することは不可能に近い。この経験から、自殺問題への対応の難しさを痛感した。
自殺者が見せる前兆とサイン
一般的な自死の前兆といえるサインには次のようなものがあると言われている。その人との関係性で3パターンに分けてみた。
なるほどと思うところだが、やはり職場で了知することは難しいが、家族であれば分かることもあるのではないだろうか。
職場などで容易に分かる場合であっても、そのような事柄を本人が発していなければ分かりようがないことは言うまでもない。
1 職場などで比較的容易に分かる前兆
・急にパチンコやギャンブルにのめり込む
・真面目な人が無断欠勤したりする
・身だしなみに気をつかわなくなる
・交通事故や軽微なけがが頻繁におこる
・少しのことで不機嫌になって怒りっぽくなる
・急激な性格の変化や態度の変化が見られる
・仕事のパフォーマンスが急激に低下する
これらは自殺問題の早期発見において重要な手がかりとなる。特に真面目で勤勉だった人が急に変化した場合は注意が必要だ。
2 交流が頻繁にあって初めて分かる前兆
・部屋にひきこもる、口数が極端に減る
・急に昔の思い出話を出したりする
・急に昔の級友や遠くに住む家族の消息を気にする
・周囲への関心がなくなる、新聞やテレビを見なくなる
・一人でいるのを寂しがるようになる
・大切なものを人にあげたり、整理する
・深酒が増える、逆にお酒がまずいという
・「死にたい」と直接的に訴えることがある
特に最後の「死にたい」という訴えは、決して軽視してはならない。これは明確なSOSのサインである。
3 ごく近しい者か本人にしか分からない前兆
・手紙や写真の整理をしたりする
・食事がおいしくない、食欲が減る
・性生活が急になくなる
・薬をためこむ
・包丁や紐を探したり隠し持つ
・自殺する場所を下見に行く
・周囲の音に敏感になる
・遺書のようなメモを書いている
これらの兆候は家族など最も近い人でなければ気づけないものだ。日本では自殺を防ぐために、家族の役割は極めて重要である。
十分な観察と傾聴の重要性
とっさの判断で自殺する人はいないという。自死に先立つ何日も前、或は何時間も前からその兆候や手掛かりがある。
先の自死した同僚の奥さんは自殺前には「夫は10月頃から元気がない様子だった」と話していた。自死を選んだのが4月だから半年ほど悩んでいたことになる。
最も顕著で警戒を要するのが、「もうやっていけない」とか、「もうどうでもいい」とか、或は「全てお終いにする」のような絶望を表現している言葉だ。開き直って言うこともあるが、常に本気で受け止めなければならない危険性がある。
「死にたい」と言ってる人は死なないと聞いたことがあるが、そんなことはない。「死にたい」と言って実際に自死を選ぶ人も多い。これは自殺問題における大きな誤解の一つである。
自殺予防のためにできること
日本で自殺を減らすためには、社会全体での取り組みが必要だ。個人レベルでできることとしては以下のようなものがある。
・周囲の人の変化に敏感になる
・「死にたい」という訴えを真摯に受け止める
・話を否定せず、まずは傾聴する
・専門機関への相談を勧める
・一人にしない、見守りを続ける
・うつ病など精神疾患の可能性がある場合は受診を勧める
自殺問題は決して他人事ではない。誰もが当事者になり得るし、誰もが支援者になり得る。実際、うつ病で死亡する人の多くは、周囲が気づいていれば救えた可能性があるのだ。
まとめ
何れにしても、周りの人に普段と違うような様子があるならば、十分な観察のもと良く話を聞くことが大切だ。
日本では自殺により毎年多くの命が失われているが、一人ひとりが自殺問題に関心を持ち、適切な知識を持つことで、救える命は確実にある。うつ病で死亡することを防ぎ、死にたいと訴える人の声を真摯に受け止め、自死を防ぐための行動を起こすことが、私たち全員に求められている。
もし周囲に「死にたい」と訴える人がいたら、決して一人で抱え込まず、いのちの電話(0570・783・556)や各地域の精神保健福祉センターなどの専門機関に相談することをお勧めする。





