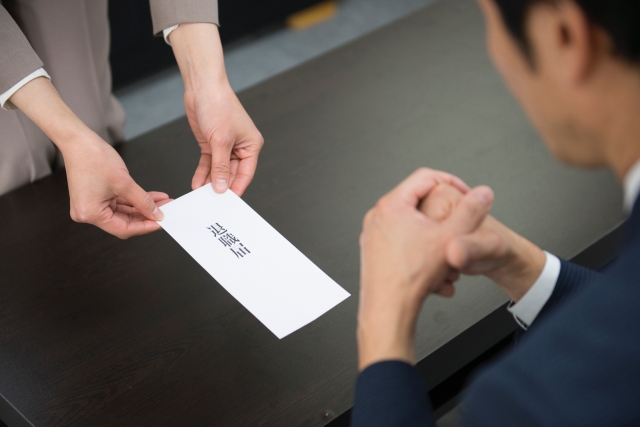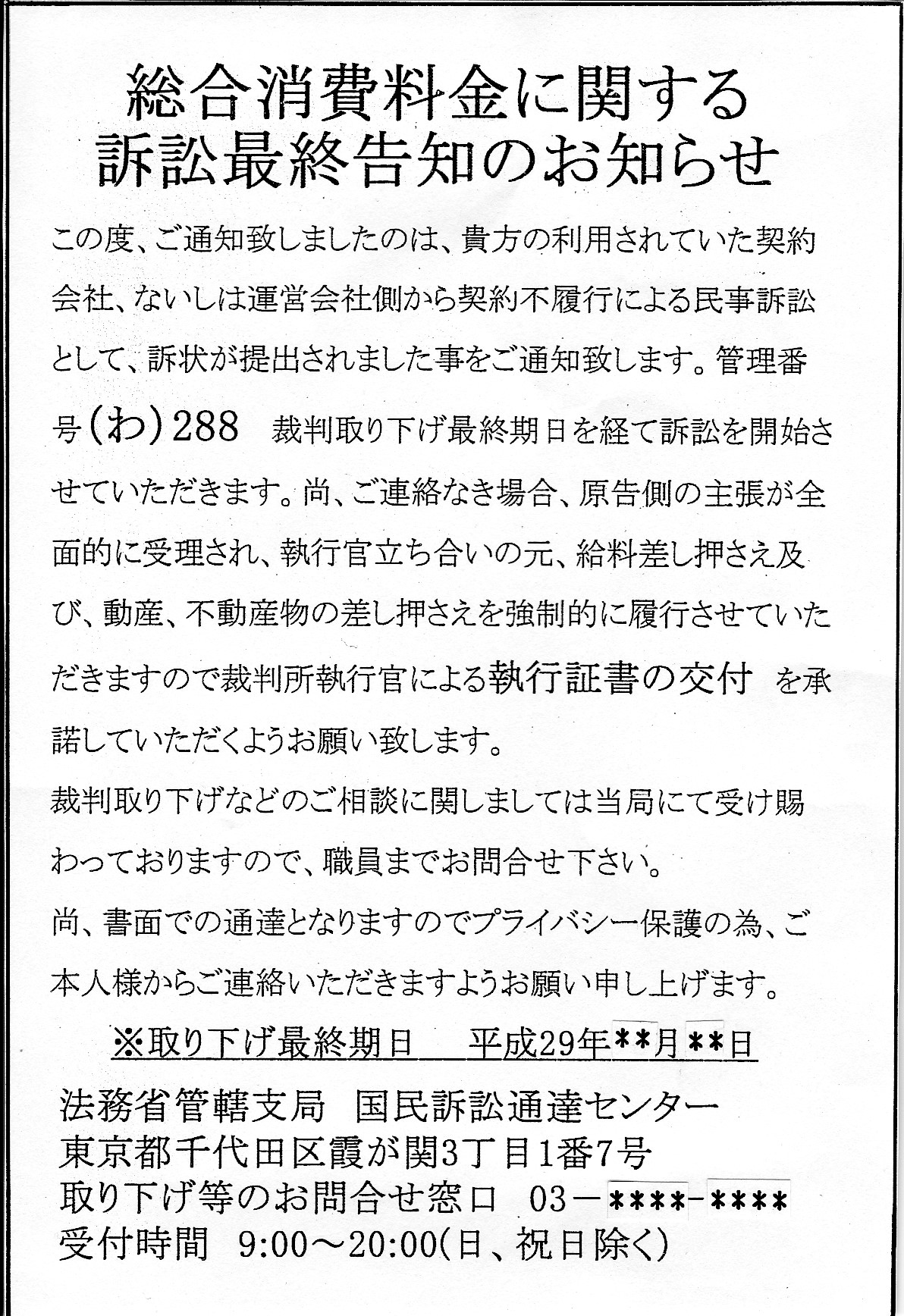平成29年2月、厚生労働省から「地域共生社会の実現に向けて(当面の改革工程)」という文書が発出された。この文書は、地域共生社会の実現をコンセプトとして掲げ、いくつかの法整備を通じて更なる改革を推進するものである。本稿では、共生社会とは何か、その背景と課題、そして地域共生社会 取り組みの具体的な内容について詳しく見ていきたい。
共生社会とは:地域共生社会が求められる背景
地域共生社会とは 簡単にいえば、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことである。
この共生社会が求められる背景には、日本社会の大きな変化がある。その昔は地域や家族同士の助け合いによって様々な課題を解決してきた。しかし近年では、核家族化の進行、共働き世帯の増加、人口の都市部への集中、個人主義の浸透などにより、そうした相互扶助の機能が弱体化してきた。その結果、かつて地域や家族が担っていた助け合いの役割を、行政が担わざるを得なくなってしまったのである。
しかしながら、行政による支援体制は分野ごとに縦割りで整備されてきた経緯があり、複雑化・多様化する現代の生活課題に対して、きめ細やかな対応ができなくなっている。また、一人の人が複数の制度を必要とするケースも増えており、さらには人口減少により支援を担う専門人材の確保も困難になってきている。このような状況から、公的支援の在り方を縦割りから「丸ごと」へと転換し、地域共生社会の実現を目指す必要性が高まっているのである。
つながりの再構築:制度の狭間にある課題
共生社会の実現において重要なのが、地域におけるつながりの再構築である。現在、既存の制度が対象としない課題も数多く出てきている。例えば、社会的孤立の問題や、身近な生活課題(電球の取り換え、ごみ出しなど)がその代表例である。これらは「制度の狭間」に位置する問題として認識されており、従来の縦割り行政では対応が難しい領域となっている。
こうした課題は、かつては地域コミュニティや家族の間で自然に解決できていたものである。しかし、地域や家族のつながりが弱まっている現代においては、改めて地域でできることを見直し、住民相互の支え合いの仕組みを構築していく必要がある。これこそが地域共生社会 取り組みの核心部分といえるだろう。
地域共生社会 取り組み:改革の骨格
厚生労働省の文書では、以下の4点を改革の骨格として位置づけている。
1. 地域課題の解決力の強化
住民が主体的に地域課題を把握し、その解決を試みる体制を構築していく。具体的には、分野を超えて「丸ごと」の相談を受け止める場を設けることが重要である。また、多様で複合的な課題については、福祉分野だけでなく、保健、医療、就労、教育、住まいなど多機関が連携し、市町村等の広域で解決を図る体制を確保する。これは共生社会 具体例として、各地域で「包括的相談支援センター」や「多機関協働の場」を設置する動きとして現れている。
2. 地域丸ごとのつながりの強化
地域の支え合い活動に関わる人材の育成を促進するとともに、地域の民間資金の活用を推進する。さらに、まちづくりや産業振興などの分野における取り組みと連携し、人と人、人と資源が「丸ごと」つながる取り組みを支援していく。この点は、共生社会 具体例として、地域食堂や多世代交流拠点の整備、企業の社会貢献活動との連携などが挙げられる。
3. 地域を基盤とする包括的支援の強化
地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地域を「丸ごと」支える包括的な支援体制を構築する。人口減少など地域の実情に応じて、制度の「縦割り」を超えて柔軟に必要な支援を確保することが容易になるよう、事業・報酬の体系を見直す必要がある。また、保健分野については、その支援体制を強化するとともに、福祉行政との連携を緊密化していく。
4. 専門人材の機能強化・最大活用
地域共生社会の実現において、支援を担う専門人材の役割は一層重要となる。人材の有効活用を図る観点から、専門性の高い人材を養成していくことが必要である。このため、各資格の専門性の確保に配慮しつつ、養成課程のあり方を「縦割り」から「丸ごと」へと見直していく方向性が示されている。
行政の役割と地域の責任:バランスの課題
ここで重要な点として、文書中では「地域づくりの取り組みは地域における住民相互のつながりを再構築することで生活に困難を抱える方へのあらゆる支援の土台を作るためのものであるが、これにより市町村や公的支援の役割が縮小するものではない」との断りが入れられている。
しかし、この文言を額面通りに受け取ることには慎重であるべきだろう。わざわざこのような念押しをしなければならないのは、「この取り組みによって行政の支援が先細りするのではないか、何が何でも地域に責任を押し付けるのではないか」という疑念が存在することの裏返しである。確かに行政の役割は形式的には縮小しないかもしれないが、その内容や程度がどのように変化していくのかについては、注視していく必要がある。
地域共生社会 取り組みの真の目的
当面の改革工程の目的を端的に表現すれば、「昔のように地域で支え合おうよ。そのための支援や環境整備を行政が行っていくよ」というものである。
興味深いのは、「昔に戻る」のであれば本来は「地域」ではなく「家族」が中心になるはずだという点である。文書の冒頭では家族の相互扶助について触れているものの、いつの間にか議論の焦点は「地域」へと移行している。かつての日本社会における相互扶助を語るならば、大家族制に基づく家族内での助け合いを抜きにしては語れないはずである。
おそらく「家族」を前面に出すと、個人の生き方や価値観を制限する可能性が高いため、政策としては採用しにくいのだろう。「皆で助け合おう」「3世代、4世代同居を推進しよう」と謳っても、それは個人の自由な選択の問題であり、政府が関与すべきことではないと批判されてしまう。だからこそ、家族ではなく地域という枠組みを用いているものと考えられる。
共生社会 具体例:介護保険制度から見える構造
介護保険制度を例に取ると、この地域共生社会 取り組みの背景がより明確に見えてくる。核家族化の進行により介護を担う家族成員が減少し、介護が社会問題化したことで介護保険制度が導入された。しかし、高齢化の急速な進行により介護保険財政は逼迫してきている。とはいえ、制度そのものを廃止することは不可能である。
そこで考えられるのが、制度を利用する人を減らすという方策である。そのためには、かつてのように地域や家族で助け合う人が増えれば良いわけである。助け合いの土壌が再構築されれば、少しでも公的な財政負担が軽減されるのではないか、というのが本音の部分であろう。
この考え方自体は、ある意味で合理的である。何でもかんでも公的扶助に頼るのではなく、自分たちでできることは自分たちで行う。これは本来あるべき姿といえる。地域には様々なスキルや経験を持った人材が豊富に存在するのだから、その地域の力を引き出し、活用するための支援を行政が行うというのは、理にかなったアプローチである。
地域は本当に担うだけの力を持っているのか
このように国は「地域共生」を掲げ、地域住民の助け合いを促進しようとしているが、実際に地域にはそのような助け合いを実現する力があるのだろうか。答えはYESである。地域には様々な専門スキルを持った立派な人材が多数存在するし、特別なスキルはなくとも「誰かの役に立ちたい」という意欲を持つ人々も大勢いる。
しかし現状では、その潜在的な力を十分に発揮できていない。その最大の理由は、明確な司令塔が存在しないからである。参加者が皆、同じ立場のボランティアであれば、効果的な指揮命令系統は成立しない。形式的には役割分担によって立場を変えているように見えても、実際には対等な関係性のままなのである。
では、役所が司令塔になれば良いのではないかと考えるかもしれないが、実際にはそうはならない。役所は地域の人々に対して、まるで腫れ物に触るかのような慎重な態度で接する傾向がある。なぜなら、相手は無報酬で善意によって活動してくれる貴重な存在だからである。その機嫌を損ねることは避けなければならないという意識が働く。
推測であるが、過去の歴史的経緯から、行政が地域に対して積極的に関与することを躊躇している面もあるのではないだろうか。また、そもそも地域共生社会の趣旨が行政の関与範囲を狭めることにあるため、行政が深く介入することは本末転倒となってしまう。
ボランティアという落とし穴
次に指摘すべき課題は、「ボランティア」という枠組みそのものが抱える問題である。ボランティア活動は基本的に責任が明確ではなく、緊張感に欠ける傾向がある。参加者からは「なぜこんなことまでボランティアでやらなくてはならないのか」という不満の声も聞かれる。
つまり、地域共生社会の実現のためには、「これはボランティア精神に基づく善意の活動である」という現状の認識を変える必要がある。「当然行うべきこと」「これが市民としての義務である」という意識にまで昇華させなければならない。しかし、こうした意識改革は決して容易なことではない。
共生社会の実現:システム構築の必要性
地域共生社会の実現には、住民の意識変容が必要であることは間違いない。しかし、意識改革を待っているだけでは前に進まない。意識が完全に変わらなくても、地域が力を発揮できる具体的な仕組みを構築する必要がある。それでは、どのようなシステムが考えられるだろうか。
ボランティア通貨の活用
一つの共生社会 具体例として、「ボランティア通貨」の導入が考えられる。これは、ボランティア活動を行うことで一定の地域通貨を受け取り、その通貨を特定の用途に使用できるようにする仕組みである。ただし、現金化はできず、現金で購入することは可能とする。いわば一種の商品券のようなものである。この範囲においては、純粋なボランティアではなく、一定の対価を伴う活動となる。
既存の取り組みとして地域通貨の実験は各地で行われているが、必ずしも機能しているとは言い難い。そのため、過去の教訓を踏まえた上で、より実効性のある制度として再構築する必要がある。
町内会の特別な位置づけ
地域共生社会 取り組みを推進する上でのキーワードは「町内会」である。もちろん、地域共生の主体は町内会だけではない。個人や様々な団体がその構成員となる。しかし、その中でも住民の生活向上を明確な目的として掲げている団体は町内会をおいて他にない。町内会をその他の団体と十把一絡げに扱ってはならないのである。
裾野を広げるという意味で、町内会以外の多くの団体にも担い手として参加してもらうことは重要である。しかし、地域共生社会の中核を担うべきは町内会であり、そのための特別な位置づけや支援が必要となる。町内会に対して、実質的な権限や予算配分、人材育成の機会などを提供することで、真の意味での司令塔機能を発揮できるようにすべきである。
民間企業の戦略的活用
共生社会の実現においては、民間企業の活用も重要な要素となる。現在のように企業の社会貢献活動やCSR活動としてのボランティア参加にとどまるのではなく、企業にとっても実益が上がるような仕組みを構築し、参加企業を増やしていく方向性が望ましい。
例えば、地域貢献活動を行う企業に対して税制上の優遇措置を設けたり、地域との連携を企業評価の指標に組み込んだりすることで、企業の積極的な参加を促すことができる。また、企業が持つ専門性やノウハウを地域課題の解決に活用することで、より質の高い支援を実現できる可能性もある。
まとめ:地域共生社会の実現に向けて
地域共生社会とは、住民一人ひとりが主体的に参画し、世代や分野を超えてつながり、支え合う社会である。その実現は、少子高齢化が進む日本社会において喫緊の課題となっている。
しかし、地域共生社会の実現には多くの課題が山積している。役所にありがちな「掛け声だけで後は野となれ山となれ」という姿勢では、真の意味での共生社会は実現できない。地域が実際に動けるような、具体的かつ実効性のある仕組みを構築する必要がある。
そのためには、行政と地域住民が互いにWIN-WINの関係となるような制度設計が不可欠である。地域住民にとっては参加することに意義や充実感があり、場合によっては一定の対価も得られる。行政にとっては公的負担が適正化され、より柔軟できめ細やかなサービス提供が可能になる。企業にとってはビジネスチャンスや社会的評価の向上につながる。
このような多方面でのメリットを創出する仕組みこそが、持続可能な地域共生社会を実現するための鍵となる。今後、各地域の実情に応じた創意工夫ある取り組みが展開され、それらの成功事例が共有されることで、日本全体で共生社会の実現が加速していくことを期待したい。