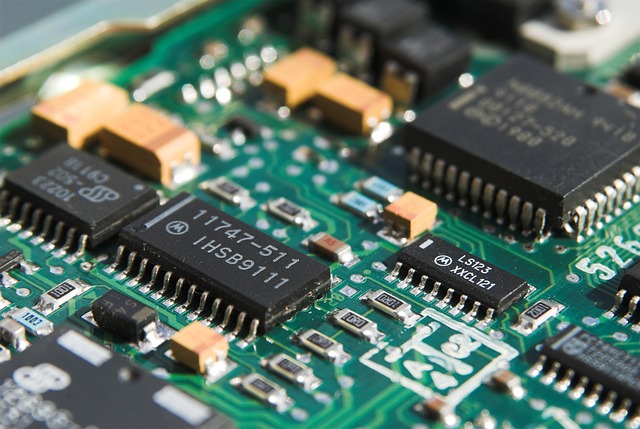
「自作pc やめとけ」と言われる前に知っておきたいこと
パソコンを自作する人は多いと思う。私のパソコンも自作品である。昔から自作をしていたものだが、生業としているわけではないので自作する頻度はそれほど多くはない。前回はメーカー製を買っていたため、今回はおよそ10年ぶりの自作となった。
「自作pc やめとけ」という意見を目にすることもあるが、適切な知識と準備があれば決して難しいものではない。ただし、10年ぶりに自作をすると昔のノウハウは殆ど役にたたず、今回は多くのミステイクをした。自作pcが時代遅れということは全くないが、技術の進化により注意すべきポイントは大きく変わっている。
以下、失敗を恥ずかしながら披露したい。巷の「こんなことに気を付けようね」といったものではなく、全て実際に私が失敗したものである。書いて見ると、よくぞここまで失敗したものとつくづく思う。みなさんも同じ轍を踏まないように。
自作pc構成を考える前に:予算設定の重要性
自作pcを始める前に、まず自作pc予算をしっかり設定することが重要だ。私の場合、明確な予算を立てずに始めたため、結果的に高価なパーツを購入してしまい、コストパフォーマンスが悪くなってしまった。
自作pc見積もりを事前に立てる際は、以下のポイントを考慮すべきである:
・ CPU、マザーボード、メモリの組み合わせ
・ ストレージ(SSD)の容量と種類
・ 電源ユニットの容量
・ 自作pcケースのサイズと拡張性
・ 冷却システム(CPUクーラー、ケースファン)
自作pc見積もりサイトを活用すれば、パーツ間の互換性チェックと同時に総額を把握できる。これにより、自作pcを安く抑えるための調整も可能になる。
私の失敗談:自作pcケース選びで失敗しないために
ケースに収まらないCPUクーラーを買ってしまった
**(教訓)CPUクーラーはケースに収まることを確認すること**
小型をコンセプトに作成したパソコンなのでMini・ITX仕様となっている。いざ、取り付けようとしてもケースに収まりきらなかった。
自作pcケース選びは自作pc構成全体に影響する重要な要素だ。パソコンケースは物によってはこのように相当小さいものもある。CPUクーラーの高さによってはケースに入らないものもあるので事前にクーラーの大きさを確認しておかなくてはならない。
自作pcケースを選ぶ際のチェックポイント:
・ CPUクーラーの最大高さ制限
・ グラフィックカードの最大長
・ 電源ユニットの設置方式(ATX、SFX等)
・ 拡張スロットの数
・ エアフローの設計
特にMini・ITXやMicro・ATXなどのコンパクトな自作pcケースを選ぶ場合は、各パーツの寸法を入念に確認する必要がある。
マザーボードのCPU接続ピンを折ってしまった
**(教訓)マザーボードの取り付けには十分注意すること**
マザーボードとCPUの接続は昔はピン方式であったが、現在はCPUにピンはなく、接続はマザーボード側についている細い端子により行われる。この細い端子は本当に弱く、すぐに折れてしまう。このため、CPUを取り付けるときは、ピタリと合う位置で上手く取り付けないとマザー側のピンが折れてしまう。決して、装着してからずらすようなことはしてはならない。
余談だが、このピンの折れたマザーボードはヤフオクで980円で売却した。こうしたマザーボードを修理して再販している人もいるらしい。この失敗だけで数万円の損失となったため、自作pcを安く仕上げる計画が大きく狂ってしまった。
マザーボードのSATA端子を壊してしまった
**(教訓)マザーボードのSATA端子の着脱に注意**
SATAの接続コードによってSATA端子側でロックがかかるものがある。そのときは、無理に取ろうとするとマザーボードのSATA端子が破損することになるので、少し力を入れて取れない場合はロックがされていないか確認しなくてはならない。
マザーボードを間違って買ってしまった
**(教訓)マザーボードの買い間違いに注意**
メーカーは、当該CPUを付けることができるマザーボードを何種類も同時に出している。同一メーカーだとネーミングの仕方が同じなので、同じCPUが使える場合は名前が酷似する。
私が失敗したのはヤフーショッピングで買ったときだが、名前検索で指定して出てきたものを買ったのだが、ヤフーショッピングの検索結果は、あいまい検索なため、似たような名前のマザーが一覧表示されていた。それに気が付かずに、枝番まで入れて検索したのだから、当該マザーだと思い買ってしまったが、Mini・ATX買ったつもりがMicro・ATXを買ってしまっていた。
自作pc構成を練る際には、マザーボードのフォームファクタ(ATX、Micro・ATX、Mini・ITX)と自作pcケースの対応を必ず確認すること。購入前には型番を完全に一致させて検索し、スペックシートで再確認する習慣をつけるべきだ。
CPUにクーラーが付いておらず、すぐに作成できなかった
**(教訓)CPUにはクーラーが付いていないものもある**
以前はBOXであれば必ずCPUクーラーが付いていたが、最近の高性能CPUでは付いていないことも多い。このため、全ての部品が揃ったと思って、いざ作成しようとしても完成しない。必ずCPUクーラーが付いているCPUかどうかを確認しておかなくてはならない。
自作pc見積もりを作成する段階で、CPUにクーラーが付属しているかを確認し、別途購入が必要な場合は予算に組み込んでおくべきだ。特にハイエンドCPUを選択する場合は、クーラー非付属であることが多い。
高価なCPUを買ってしまった
**(教訓)CPUを変えても大きなスピードアップとはならない。速度は値段と直線的に比例しない**
確かにパソコンの自作の目的はCPUの高速化にあるが、結果として大した高速化にはならなかった。
自作pc予算の配分を考える際、最も重要なのは「どこに投資すべきか」という優先順位だ。CPUに予算を集中投下するよりも、SSDやメモリに適切に配分した方が、体感速度の向上につながることが多い。自作pcを安く仕上げつつ性能を確保するには、ミドルレンジのCPUと高速なストレージの組み合わせが効果的だ。
M.2 SSDを買うつもりがSATA接続のSSDを買ってしまった
**(教訓)起動用のSSDは間違えずにM.2 SSD接続にすること**
ストレージはSSDを選択しなくてはならない。ストレージはハードディスクが安価で容量が多いので選択しがちであるが、今はSSDが安くなっているので必ずSSDにする必要がある。SSDの方が速度がとても違うのでCPUを良いものにするよりも体感速度は大幅にアップする。
起動用のSSDはM.2 SSD接続とSATA接続のものがあるが、価格は高くなるが必ずM.2 SSDにしないとならない。そのつもりで買ったのだったが、間違ってSATA接続のものを買ってしまった。形が全く同じなので間違えやすい。
自作pc構成でストレージを選ぶ際は、以下を確認すべきだ:
・ インターフェース(M.2 NVMe、M.2 SATA、2.5インチSATA)
・ 転送速度(NVMeの世代:Gen3、Gen4、Gen5)
・ マザーボードの対応M.2スロット数
・ ヒートシンクの有無
壊れた電源を開けてしまいメーカー保証を受けれなくなった
**(教訓)メーカー保証が付いているものはむやみに解体しない**
パソコンの電源が特に何もしていないのに壊れた。ヒューズが切れているのではないかと電源を開封(開封と言う表現があたってるかどうかは分からないが要は蓋を開けた)してヒューズを見たが切れていなかったのでお手上げとなり、買ったばかりだったのでメーカーに修理を依頼した。しかし、開封品は受け付けられないと断られた。
自作pc予算を抑えるために安価な電源を選びがちだが、電源ユニットは自作pc構成の中でも特に重要なパーツだ。80 PLUS認証(Bronze、Silver、Gold、Platinum、Titanium)を取得した信頼性の高い製品を選び、保証期間も確認すべきである。
「自作pc 時代遅れ」は本当か?
一部では「自作pc 時代遅れ」という意見も聞かれるが、これは誤解だ。確かにメーカー製PCの性能は向上し、価格も競争力を持つようになった。しかし、自作PCには以下のメリットがある:
・ パーツ選択の自由度が高く、用途に最適化できる
・ 将来のアップグレードが容易
・ 故障時の修理が容易で、パーツ単位での交換が可能
・ 自分の手で組み立てることによる満足感と学習効果
・ 長期的には自作pcを安く維持できる可能性
特に、自作pc予算を適切に配分し、自作pc見積もりを綿密に立てれば、メーカー製PC以上のコストパフォーマンスを実現できる。
まとめ:失敗から学ぶ自作PCの成功法則
「自作pc やめとけ」という声に惑わされず、これらの失敗事例を参考にすれば、初めての自作でも成功する可能性は高い。重要なのは:
1. 自作pc予算を明確に設定する
2. 自作pc見積もりを事前に作成し、パーツの互換性を確認する
3. 自作pc構成を慎重に検討し、用途に合ったパーツを選ぶ
4. 自作pcケースとパーツのサイズ互換性を必ず確認する
5. 焦らず、説明書をよく読んで組み立てる
これらのポイントを押さえれば、自作pcは決して時代遅れではなく、むしろ自分だけの最適なシステムを構築できる素晴らしい選択肢となる。自作pcを安く、かつ高性能に仕上げることは十分可能だ。
私の失敗が皆さんの成功の糧となれば幸いである。





