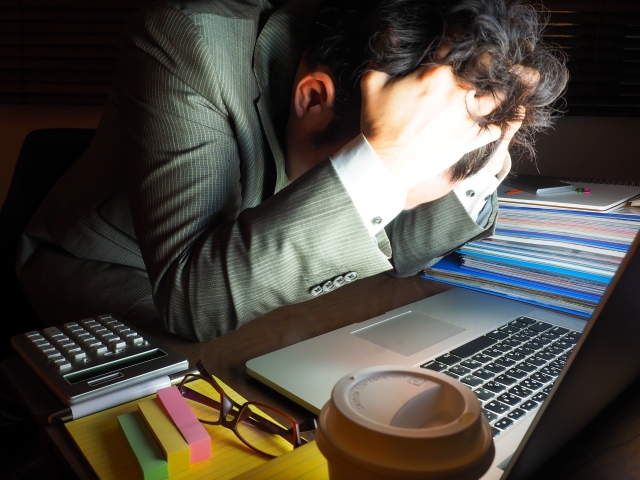選択的夫婦別姓をめぐる日本の現状と世論
選択的夫婦別姓の議論が盛んになっている。この制度について議論することは非常に良いことだ。各種アンケート調査では若干「選択的夫婦別姓 反対」の意見が多いようだが、これは70代以降の高齢層で反対が多いためである。この70代以降で選択的夫婦別姓に反対が多いのは、昔の「家」という概念がまだ根強く残っているからだろう。
興味深いことに、70代未満の世代では逆に賛成が多くなっている。若い世代ほど選択的夫婦別姓の導入に前向きな傾向が見られる。このため、将来的には選択的夫婦別姓の制度が日本でも実現される可能性が高いと考えられる。
選択式夫婦別姓制度でも同姓を選ぶ人が多い?
選択的夫婦別姓が可能となっても、実際には結婚後は同一姓を名乗るとする者の方が多いだろうという予測は興味深いところだ。これは「選択式夫婦別姓」という制度の本質を表している。つまり、強制ではなく選択肢を増やすという点に意義があるのだ。
選択的夫婦別姓の議論はなかなか難しく、メリットもあればデメリットもある。だからこそ、様々な角度から慎重に検討する必要がある。
賛成派と反対派の主張を比較する
選択的夫婦別姓の導入を認めるべきとする主な理屈は「96%もの夫婦で夫の姓を名乗っており、男女不平等だから」というものだ。現状の夫婦同姓制度では、選択的夫婦別姓の制度にしないと男尊女卑が解消されないという主張である。
一方、選択的夫婦別姓 反対の立場からは、家族の一体感がなくなるとか、親の姓が違うと子供に悪影響があるなどという意見が出されている。また、伝統的な家族観が損なわれるという声や、「選択的夫婦別姓 おかしい」と感じる人々からは、社会の混乱を招くのではないかという懸念も表明されている。
しかし、両者の主張とも決定的な説得力に欠けるように思える。
男女不平等論の検証
男女不平等という主張について考えてみよう。法律で必ず男性の姓を名乗るようにと定められているのなら確かに不平等だが、夫婦が互いに話し合った結果そうなったに過ぎないのであれば、それを不平等と呼ぶのは適切だろうか。
もちろん、現実的に女性ばかりが姓を変えているし、変えなくてはならない社会的雰囲気が問題となるのは事実だ。しかし、それは「啓蒙」の話であって法律論とは別の次元の問題ではないだろうか。夫婦別姓という選択肢を法的に用意することと、社会の意識改革は、両輪として進めるべき課題なのかもしれない。
子供への影響は本当にあるのか
親の姓が違うと子供に影響するという「選択的夫婦別姓 反対」の意見は、子供が不安に感じたり、いじめに遭ったりする可能性を指摘しているのだろう。しかし、選択的夫婦別姓が当たり前の社会になっていれば、そうした問題も自然と解消されていくはずだ。
家族の一体感がなくなるという懸念についても、そんな気がする一方で、そうはならない気もする。夫婦別姓であっても家族の絆は変わらないという人もいれば、やはり姓が統一されていることに意味を感じる人もいるだろう。
重要なのは、選択的夫婦別姓で夫婦同一の姓を認めないなら大問題だが、どちらでも良いとするのであれば選択肢が広がって好ましいという点だ。これこそが「選択式夫婦別姓」の本質である。
選択的夫婦別姓 世界の状況はどうなっているのか
ここで「選択的夫婦別姓 世界」の状況を見てみよう。実は、多くの先進国では既に夫婦別姓や選択的夫婦別姓が認められている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど欧米諸国の多くでは、結婚後も旧姓を使用することが一般的に認められている。
アジアでも、韓国や中国では伝統的に夫婦別姓が基本だ。タイでも選択的夫婦別姓の制度が存在する。むしろ、夫婦同姓を法律で義務付けている国は世界的に見ても少数派なのだ。
こうした「選択的夫婦別姓 世界」の潮流を見ると、日本が選択的夫婦別姓の導入を検討するのは自然な流れとも言える。ただし、各国の文化や歴史的背景は異なるため、単純に海外の制度を模倣すれば良いというものでもない。
日本人のアイデンティティは変わってきたか
日本人は個より全体を重んじる国民性である。個々の意見よりも全体の意見が正しいとする傾向が強い。全体の意見が実は声の大きい個人の意見という場合もあるが、何れにしても全体でオーソライズされた事柄に従う傾向が強い。
企業が不祥事を起こしたときに、テレビカメラの前で一列に並んで謝罪する姿を見て人々は溜飲を下げる。本来不祥事の当事者間で謝罪すれば済むだけなのに、社会全体に対して謝罪しなければ「良し」としない国民性なのだ。
このように個より全体という考え方に凝り固まっている面がある。個を主張すると自分勝手、協調性がないと後ろ指を指される。太宰治が『人間失格』で「世間とは何だ」と問うた社会は、連綿として続いている。
一方、欧米はそうではない。個人個人の行動が全てである。個人個人の考え方を尊重する個別的社会だ。選択的夫婦別姓の議論を聞いていて、ようやく日本も欧米的な個人主義に近付いたのかと感じることがある。
選択的夫婦別姓の導入で社会はどう変わるか
とは言っても、選択的夫婦別姓が進んで夫婦別姓が一般的な社会となったらどうなるのだろうか。自分の両親の姓が違っていたらちょっと戸惑う気持ちもある。隣の家を指すときに山田さんと言えば良いのか田中さんと言えば良いのか分からなくなる場面も出てくるだろう。
離婚しやすくなるような気もする。姓を変えていないことで、心理的なハードルが下がるかもしれない。墓にはどうやって入るのだろうかという素朴な疑問もある。
結婚するときに、片方が夫婦別姓を望み、もう片方が同姓が良いと夫婦間の考えが違うと、新たなもめる原因になるのではないか。今なら、暗黙の了解で男性の姓を名乗るというコンセンサスがあるから、その点では大丈夫なのだろうが。
選択的夫婦別姓 制度設計の課題
選択的夫婦別姓 制度を導入するにあたっては、様々な実務的な課題もある。子供の姓をどうするか、戸籍制度をどう変更するか、各種手続きでの本人確認はどうするかなど、検討すべき点は多い。
また、選択的夫婦別姓 制度が導入されたとしても、それが社会に定着するまでには時間がかかるだろう。過渡期には混乱も予想される。しかし、それは新しい制度が定着する過程では避けられないことかもしれない。
まとめ:夫婦別姓がもたらす社会の変化
夫婦別姓、あるいは選択式夫婦別姓の社会は、確かにちょこっと不便な面が出てくることは間違いない。しかし、それは新しい選択肢を得るための小さなコストと考えることもできる。
重要なのは、選択的夫婦別姓 制度によって、個人の選択の自由が広がるという点だ。同姓を選びたい人は同姓を選べばよいし、別姓を望む人は別姓を選べる。それが真の意味での「選択的」ということだ。
「選択的夫婦別姓 おかしい」という感覚を持つ人がいるのも理解できる。長年続いてきた制度や慣習が変わることへの抵抗感は自然なものだ。しかし、時代とともに社会は変化していく。選択的夫婦別姓の導入についての議論は、まさに日本社会が個人の多様性をどこまで尊重できるかという試金石なのかもしれない。