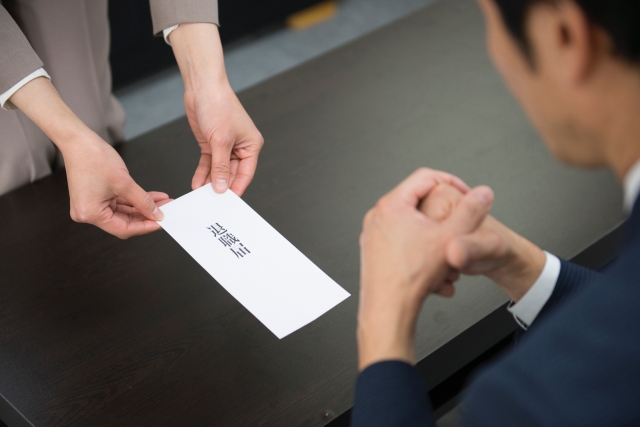孤独死とは ・ 誰にでも起こりうる現実
孤独死とは、誰にも看取られることなく、一人きりで亡くなり、その後しばらく発見されない状態を指します。高齢者に限らず誰もが孤独死のリスクを背負う時代になっています。
孤独死はしたくない。誰もがそう思います。しかし、現実には後を絶ちません。うちは夫婦で住んでいるから大丈夫と言っても、配偶者はいつかはいなくなります。残った者は必ず一人となり、孤独死の予備軍となるのです。
孤独死は高齢者だけの問題ではない ・ 若者の孤独死も増加
孤独死するのは何も高齢者に限りません。近年、孤独死若者の事例も増加傾向にあります。私の知り合いの子供は24歳で夭折しました。単身アパート暮らしで、くも膜下出血でした。
孤独死若者死因として多いのは、突然の病気や事故です。若いからといって油断はできません。一人暮らしの若者も、高齢者と同様に孤独死のリスクを抱えているのです。過去には、孤独死したアイドルのケースも報道され、社会に衝撃を与えました。若くして活躍していた人でも、一人暮らしの環境では孤独死のリスクから逃れることはできないという事実を、私たちは認識する必要があります。
孤独死対策 ・ 行政は頼りにならない現実
孤独死対策として、行政が何とかしてくれると考えるかもしれません。しかし、行政が目指すのは亡くなった後の早期発見であって、孤独死をゼロにしようとは思っていません。
私は、その昔、行政の見守りを考える施策を検討したことがありましたが、そのときの結論は「もっと行政が見守りを行う方策を今後とも考えるべき」という抽象的な内容で終了しました。行政職員が一人ひとりを見守ることは不可能なため、行政はこういった結論にしかならないのです。
行政ができるのは、様々な団体が進める見守り活動を支援することしかできません。例えば、民生委員の見守り、新聞社や配送業者などの見守り、町内会などの見守り活動に対して、技術的、資金的にバックアップをすることです。
こうした団体が異変を察知し、最終的に行政に連絡が来ることになります。
## 孤独死警察対応と遺体発見の流れ
行政はどのようにその対応を行うかを紹介したいと思います。まず、当然、現地を確認します。このとき、貯まっている新聞やチラシの状況、電気のメータなどを確認し、ポストに連絡票を投函し、翌日にその連絡票がどうなっているか(読まれたか)を確認します。同時に、身内の情報、通院状況なども分かる範囲で確認します。身内の存在が分かればすぐに連絡を入れます。
いざいざ、異変の可能性(中で亡くなっている可能性)があれば、大家に連絡し、孤独死警察への通報を行って開錠し、中に入るという手順になります。孤独死遺体が発見された場合、警察による検視が行われます。孤独死部屋の状況も詳しく調査され、事件性がないかどうかが確認されます。
孤独死事故物件化のリスク
孤独死が発生した部屋は、発見が遅れるほど孤独死事故物件として扱われるリスクが高まります。特に夏場など、孤独死遺体の腐敗が進んだ場合、孤独死部屋の原状回復には多額の費用がかかります。これが孤独死事故物件として次の入居者に告知する義務が生じる原因となるのです。
賃貸物件の場合、遺族や保証人に対して原状回復費用や家賃補償が請求されることもあります。孤独死対策は、本人のためだけでなく、残された家族のためにも重要なのです。
町内の見守りは機能するか
行政などは、日ごろからの町内単位での見守り活動を勧めていますが、確かに「あの人最近見ないね」というときの遺体の発見には役に立つかもしれませんが、いざ異変が生じたそのタイミングでたまたま隣近所の人が来るということは期待できないので、効果には疑問符が付きます。
加えて、町内の見守りでは見守りを阻むものの存在があります。それは、個々人の干渉されたくないという気持ちです。見守りはすなわち、個人のプライバシーに立ち入ることでもあります。見られている、見張られているというように捉えられてしまうことがあるのです。
このように行政が進める見守りは、機能的でないばかりか異変発生から早くて数日というタイムラグがあります。一人住まいで、いざ体調が悪くて救急車を呼ぶことができなくなったときには頼りになりません。1週間で発見された場合、「早期発見で良かったね」となるかもしれませんが、当の本人にとってはそうではありません。異変が生じたその瞬間に亡くなることができたならまだしも、何日も苦しんだ結果の死であれば哀れとしか言いようがありません。我々は異変が発生してから生きている間に救急車を呼んでもらいたいのです。
個人個人の孤独死対策が必要
行政や町内の見守りが頼りにならないとすると、我々は異変が生じたときにすぐにできる対応を、個人個人で考えておかなくてはなりません。以下、私が考える手段です。
民間サービスを利用する
民間サービスとしては例えば象印で行っているサービスがあります。こちらは、一定時間ポットを使わないと登録している者に通知が行くというもの。お金はかかりますが、お金の問題で済むなら煩わしいことはありません。高齢者同士が互いに連絡先としても良いでしょう。
食事を届ける宅配弁当という手もあります。毎日、手渡しで弁当を授受していて連絡がなく受け取りに出てこない場合に対応を依頼するというものですが、こちらも若干のタイムラグが生じるので、出てこない場合の対応を事前に決めておくなどした方が良いです。
これらのサービスは、孤独死対策として有効であるだけでなく、万が一の際に孤独死事故物件化を防ぐことにもつながります。
施設に入るという選択
私は、何らかの介護サービスを使うことができるようになっているなら、まずは施設に入ることを勧めます。特別養護老人ホームは要介護が高くなければ入れず、そもそも居宅生活を送ることができるような人は対象外なので、サービス付き高齢者住宅、俗に言う「サ高住」が良いです。
サ高住は最近本当に充実してきましたし、個室対応となっておりプライバシーも守られます。もちろん、見守りは本当に充実しています。食事のときに食堂に来なければそれだけでも見守りとなります。孤独死高齢者のリスクを大幅に減らすことができる有効な選択肢です。
親族等と同居する
核家族となって久しいですが、独り身となったときには子供などに頼るべきものと思います。子供からの同居のオファーを断るという人が結構いるらしいですが、他意がない、子供が純粋に親を心配してのオファーなら素直に受けるべきです。
年老いた兄弟がいるという場合は兄弟同士の同居も考えられます。仲の良い友達との同居も良いでしょう。誰かが周りにいる環境を作るのです。同居することで、孤独死のリスクは大幅に減少します。
孤独死葬儀と事後対応
万が一、孤独死が発生した場合、孤独死葬儀の手配が必要になります。身寄りがいない場合は、行政が火葬のみを行う場合もありますが、可能であれば遺族が孤独死葬儀を執り行うことが望ましいです。
孤独死遺体の発見後は、孤独死警察による検視、孤独死部屋の清掃と原状回復、そして孤独死葬儀という流れになります。孤独死事故物件としての処理も必要になる場合があります。
これらの事後対応は、遺族にとって大きな負担となります。だからこそ、生前からの孤独死対策が重要なのです。
まとめ ・ 今日から始める孤独死対策
孤独死とは、誰にでも起こりうる現実です。孤独死高齢者だけでなく、孤独死若者も増加しています。行政の見守りには限界があり、個人個人での孤独死対策が不可欠です。
民間サービスの利用、施設への入居、家族との同居など、自分に合った方法を選択し、孤独死のリスクを減らすことが大切です。また、孤独死事故物件化を防ぐためにも、早期発見の仕組みを整えておくことが重要です。
孤独死警察への通報、孤独死遺体の処理、孤独死部屋の原状回復、孤独死葬儀など、万が一の際の流れも理解しておくことで、遺族の負担を軽減することができます。
今日から、自分や家族の孤独死対策について、真剣に考えてみませんか。